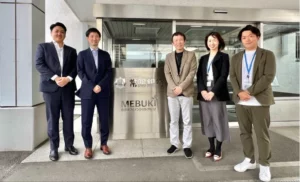インタビュイープロフィール
第一生命保険株式会社 セールスプロモーション部 オンラインマーケティング課 三上 智貴様
第一生命保険株式会社 セールスプロモーション部 オンラインマーケティング課 松平 咲乃様
課題
▪️検討期間が長い生命保険商品の特性上、LP(ランディングページ)に訪れたユーザーの多くが資料請求前に離脱してしまう課題を抱えていた
▪️クッキーレス(💡ワインポイント解説にて後述 )環境下では従来のリターゲティング広告が機能せず、離脱ユーザーへの再アプローチが困難になっていた
▪️ LINE公式アカウントの運用にも取り組んでいたが、1メッセージごとの費用が積み上がり、コスト面で持続性に不安があった
決め手
▪️ 初期費用不要で「完全成果報酬型スキーム」(💡ワインポイント解説にて後述 )で導入でき、費用対効果が明確だったこと
▪️中長期的な視点でユーザーを階段的にナーチャリング(💡ワインポイント解説にて後述 )が可能となる点
▪️ 個々のユーザー体験に寄り添ったコミュニケーションにより、継続的な接点を築ける点
結果
▪️ シナリオ経由での資料請求獲得が安定的に積み上がり、マーケティング成果を確実に計上
▪️ ランディングページにポップアップを設置し、PDCAを回しながら改善を重ねた結果、LINE友だちの獲得数が着実に増加
▪️シナリオ配信時に各ユーザーに最適なタイミングや商品を柔軟にカスタマイズができたことで、よりユーザーとの関係性が深まり、ロイヤリティ向上に貢献
生命保険という商品は、検討から契約に至るまでに長い時間を要するため、LPに訪れたユーザーの多くが資料請求に至らず離脱してしまう。第一生命保険株式会社もまた、この業界特有の課題に直面していました。さらにクッキーレス時代の到来により、従来のリターゲティング広告では離脱ユーザーへの再アプローチが難しくなっています。 そこで新たな接点として活用が進むのがLINE公式アカウントですが、ここでも1メッセージあたりのコストが発生するため、十分な数のユーザーに継続的に情報を届けようとすると費用が膨らんでしまい、効率的な運用の妨げとなっていました。その打開策として導入されたのが、Capexが提供する「PickUp」です。PickUpは完全成果報酬型スキームを採用しているため、成果が出た分だけコストが発生します。 また、LINEとの連携により、ユーザーの属性や行動に応じて最適化されたメッセージを段階的に配信することで、中長期的なナーチャリングを効率的に実現。その結果、費用対効果の大幅な改善に加え、 継続的なリード獲得と顧客ロイヤリティの向上につながっています。
第一生命様とは、2023年9月から本格的にお取引を開始し、現在で約2年にわたってご一緒させていただいています。最初は弊社のキャラクタープラットフォームをご導入いただき、そこから幅広い部門の皆さまと継続的にコミュニケーションを重ねてきました。その取り組みの延長線上で、資料請求の強化やナーチャリング施策に関する新たなご提案として「PickUp」の導入へとつながりました。
本記事では、その導入に至る経緯や具体的な成果について第一生命保険株式会社 セールスプロモーション部 オンラインマーケティング課の三上 智貴様と松平 咲乃様に、PickUpをどのように活用し、どのような成果を上げているのか、そして導入の背景にあるリアルな課題感について伺いました。
💡 ワンポイント解説:クッキーレスとは?
───────────────
従来のWeb広告では、ユーザーの行動履歴をCookie(クッキー)という小さなデータファイルで追跡していました。しかし、プライバシー保護の観点から、Apple SafariやGoogle Chromeなどの主要ブラウザがCookieの制限を強化しています。これにより、一度サイトを離脱したユーザーに対して「あの商品、もう一度見てみませんか?」といったリターゲティング広告を配信することが困難になっています。
💡 ワンポイント解説:完全成果報酬型とは?
───────────────
従来の広告やマーケティングツールは、効果に関わらず月額固定費や初期費用が発生するのが一般的です。しかし完全成果報酬型では、実際に「資料請求」や「問い合わせ」などの具体的な成果が発生した場合のみ費用が発生します。これにより、予算を無駄にするリスクを最小限に抑え、確実にROI(投資対効果)を測定できるメリットがあります。
💡 ワンポイント解説:顧客ナーチャリングとは?
───────────────
ナーチャリング(Nurturing)とは「育成」を意味し、まだ購入に至っていない見込み客に対して継続的に価値のある情報を提供し、徐々に購買意欲を高めていく手法です。特に生命保険のような高額で検討期間の長い商品では、一度の接触で契約に至ることは稀。段階的に信頼関係を築きながら、適切なタイミングで購入へと導くプロセスが重要となります。
デジタル×リアルで描く、第一生命の新しい顧客体験戦略
──本日は貴重なお時間ありがとうございます。それではまず、自己紹介と御社の事業概要について教えていただけますか?
三上様:第一生命保険株式会社でオンラインマーケティング課に所属しております、三上と申します。
松平様:同じくオンラインマーケティング課の松平です。弊社は、保障と資産形成・承継の両面から顧客に最適な商品やサービスを提供する生命保険会社です。全国の「生涯設計デザイナー」を通じて、顧客一人ひとりに合ったライフプランをサポートしています。
──セールスプロモーション部は、どのようなミッションを担っている組織なのでしょうか?
三上様:セールスプロモーション部は2025年に新設された組織です。ミッションは「リアルとデジタルの融合によるCX(顧客体験価値)の向上」と「生産性の向上」です。具体的には、データを活用したマーケティングの推進や、オフラインとオンラインを組み合わせたクロスメディアプロモーションの展開、顧客対応力の強化などを担っています。
──その中で、現在特に注力されているテーマや課題はどのようなものですか?
三上様:私たちオンラインマーケティング課の主なミッションは「オンラインを起点としたリード創出」と「データドリブンマーケティングの遂行」です。具体的には、Web上での資料請求や保険相談に至るまでの導線設計、広告出稿のディレクション、新たなプロモーションの検証などを担当しています。特に生命保険は契約までのリードタイムが長いため、いかに離脱を防ぎ、資料請求につなげるかが大きな課題となっています。
離脱を防ぎ、顧客体験を磨く ― 保険業界のデジタルマーケティング最前線
──金融・保険業界は変化が大きい中で、特に注力している課題やチャンスについて教えてください。
三上様:生命保険はご検討からご契約に至るまでのリードタイムが非常に長い商品です。資料請求に至る前に離脱してしまうユーザーが大半を占めており、ここが大きな課題でした。また、クッキーレス 環境下ではLP流入ユーザーへのリターゲティングが難しくなり、再アプローチが制約される点も悩みのひとつです。
──そうした課題に対して、UXの観点からどのような広告施策を展開されていますか?
三上様:広告から資料請求に至る導線を最適化することを基本に取り組んでいます。広告クリエイティブやLPの改善、フォーム最適化などを通じ、UI/UXを向上させるべくPDCAを回しています。
──広告施策は縦割りで担当が分かれるケースもありますが、御社の場合はいかがでしょうか?
三上様:当社のセールスプロモーション部は新設された組織で、部全体で施策を考えています。オフラインのプロモーション部門も統合されており、課をまたいでフレキシブルに取り組めるのが強みです。リード創出という共通の目的に向け、複数のチャネルを横断的に活用しています。
課題の先に見えた答え ― PickUpとの出会いが変えた第一生命の顧客戦略
──PickUp導入前には、どのような課題があったのでしょうか?
三上様:生命保険は契約までの検討期間が長いため、ランディングページを訪れても資料請求まで進まずに離脱してしまうユーザーが多くいました。そこで従来はリターゲティング広告で再アプローチしていましたが、クッキーレス環境の広がりにより十分な効果を得られなくなっていました。さらに、LINE公式アカウントを活用した配信も行っていましたが、1メッセージごとにコストがかかるため、長期的な運用には課題が残っていました。
──そんな中でPickUpを導入し、実際に使ってみてどう感じられましたか?
三上様:PickUpを導入したことで、ユーザーごとに最適化されたシナリオ配信が可能となり、中長期的な関係構築を実現できるようになりました。さらに、完全成果報酬型の仕組みにより、初期費用をかけずに安心して導入できた点も大きな魅力です。費用面でも、LINEの通常配信が1メッセージごとにコストが発生するのに対し、PickUpは成果に応じた費用だけで運用できるため、効率的な投資が可能です。こうした点が、導入を決める大きな後押しとなりました。
松平様:現状は一律のシナリオ配信ですが、今後はユーザーの流入元や関心に応じた最適化に取り組み、さらに効果を高めていきたいと考えています。
──導入後の効果について教えてください。
三上様:LPに設置したポップアップ施策により、LINE友だちの獲得数は着実に増加しました。さらに、シナリオ配信を経由した資料請求も安定して積み上がっています。加えて、ここのユーザーに合ったシナリオを通じた継続的なコミュニケーションにより、ユーザーのロイヤリティも少しずつ高まっている実感があります。
長い検討期間を価値に変える──第一生命の顧客体験イノベーション
──今後、Capexに期待されることや、取り組んでみたい新しい施策について教えてください。
三上様:LINEのリターゲティング配信をはじめ、ユーザーにとって邪魔にならないUXをどう実現するかが重要だと考えています。LPの離脱ポイントや回遊状況をヒートマップやGAで把握し、最適なタイミングでポップアップを出せるようPDCAを回していきたいです。また、流入元やユーザー属性ごとにシナリオを切り分け、早期に刈り取る層と中長期でナーチャリングすべき層を明確にすることも目指しています。
──ユーザー体験の設計において、特に重視している要素は何でしょうか?
三上様:一番大事にしているのは「ユーザーにとって邪魔にならないこと」です。スクロール中に唐突にポップアップが出てしまうと離脱につながる恐れがあります。ですから、離脱しそうなタイミングや理解が止まっているポイントを見極めて表示するなど、UXを損なわない仕組みづくりを重視しています。
──将来的には、どのような顧客接点を目指していきたいとお考えですか?
三上様:今後は流入元や広告の内容に応じてシナリオを切り分け、よりOne to Oneに近いコミュニケーションを実現していきたいです。また、資料請求だけでなく「相談したい」といったニーズを持つユーザーに応えられるチャットボットや、LINE上で生涯設計デザイナーと直接つながれる仕組みなども将来的には検討したいと思っています。
松平様:同感です。流入経路や興味関心に応じてきめ細やかなコミュニケーションを行うことで、当社へのロイヤリティをさらに高めていければと思います。
──コンテンツ展開の方向性については、どのようにお考えですか?
三上様:商品訴求だけではなく、シーズナリティや暮らしに役立つ情報など、多様なコンテンツを充実させていくべきだと考えています。一方的に「資料請求してください」と迫るのではなく、ユーザーにとって有益な情報を提供することで、ロイヤリティを育む方向にシフトしていきたいです。
──最後に、将来に向けた全体的な展望をお聞かせください。
三上様:ユーザー属性や流入元ごとに解像度を高め、最適化されたナーチャリングを実現したいと思っています。コンテンツの幅を広げながら、オンラインとオフラインをシームレスにつなぐことで、毎月安定したリード創出につながる仕組みを築いていきたいです。
松平様:One to Oneに近いコミュニケーションを通じて、ユーザーに寄り添う形でロイヤリティを高めていける未来を描いています。
💡 ワンポイント解説:One to Oneマーケティング
───────────────
One to Oneマーケティングとは、顧客一人ひとりの属性、行動履歴、興味関心に基づいて個別最適化されたコミュニケーションを行う手法です。例えば「30代女性・子育て世代・教育費に関心」の方には学資保険の情報を、「50代男性・管理職・退職後の生活に関心」の方には個人年金の情報を配信するなど、まさに「一人ひとりに寄り添った」マーケティングを実現します。
──今回の取り組みを出発点に、今後も第一生命様と共に新しい顧客体験を創り続けていければと考えています。本日は貴重なお話しをありがとうございました。
Capexでは、今後もお客様の事例をご紹介してまいります。その他のインタビュー記事もぜひご覧ください。
インタビュープロフィール
常陽銀行 ダイレクト営業部 企画グループ 次長 市川 友英 様
常陽銀行 ダイレクト営業部 企画グループ 主任調査役 浦井 祐美 様
常陽銀行 ダイレクト営業部 企画グループ 調査役 小原 太輔 様
課題
▪️ 費用対効果が最大化し切れていなかったWeb広告施策
SEOや広告で当行サイトへの流入を増加させても、8〜9割が申し込み前に離脱してしまい、費用対効果が最大化しづらい状況だった。
▪️ cookieレス対応への限界
従来のcookieを用いたリターゲティング広告などの施策は、cookie規制が強まる環境下での活用が困難になってきていた。
解決策
▪️ PickUpの導入とLINEの活用
「LPからの離脱直後」に顧客をLINEへつなぎ、メッセージを配信。商品の特性に合わせ、ローン領域ではすぐにアクションを促すメッセージを、NISAなど資産運用領域では、段階的に関心を高める情報提供を行うなど、商品特性に応じて配信スタイルを使い分けた。
▪️ 柔軟なシナリオ設計と月次改善
季節施策やキャンペーンを踏まえた配信シナリオを都度設計し、毎月の成果レポートをもとに改善を重ね、PDCAサイクルを継続的に回していった。
結果
▪️ 月間100〜150件の獲得増(カードローン)
導入初期から明確な効果が現れ、他商品への展開にもつながった。
▪️ タイミングをみたスポット配信で、着実な獲得数の積み上げが図れた
1日に3〜5件の追加獲得につながる施策事例の創出
▪️ LINEを通じた継続的ナーチャリングの確立
NISAなど「即決されにくい商材」でも、LINE経由で気軽かつ持続的な接点を持つことに成功。
「広告で多くのユーザーを集客しても、8〜9割が申込前に離脱してしまう」。 そんな悩みを抱えていたのが、茨城県を中心に地域に根ざした金融サービスを展開する常陽銀行様です。
昨今、非対面チャネルの重要性が高まる中で、Web広告やSEO施策を通じて流入数は確保できていたものの、申込完了まで至らないケースが大半を占めていました。 こうした課題に対する新たな打ち手として導入されたのが、LINEを活用した顧客コミュニケーションソリューション「PickUp」でした。
導入の決め手となったのは、ユーザーが離脱した“まさにその直後”に、LINEという生活に溶け込んだチャネルを通じて、自然にアプローチができるという点でした。まずはローン領域からトライアルが始まり、確かな成果を背景に、現在ではNISAなど資産運用領域への展開も進んでいます。
本記事では、PickUpを実際に導入・運用されている常陽銀行のご担当者様に、導入の背景や具体的な成果、今後の展望について詳しくお話を伺いました。非対面の顧客接点をどう強化し、成果につなげていくか、-そのヒントが詰まったインタビューです。

非対面での価値提供を、より確かなものに
──本日はよろしくお願いします。はじめに、皆さまのご所属とご担当領域を教えてください。
市川様:私たち企画グループは、店舗を介さない“非対面”チャネルで、さまざまな商品やサービスを顧客にご提案する役割を担っています。具体的にはWeb、DM、アプリなどを通じたマーケティング活動や、申し込み・契約につなげるための企画立案・運用を集中的に行う組織です。
私はそのグループの責任者として、非対面施策全体を統括しており、ネット広告をはじめとした各チャネルの戦略設計にも関わっています。
実は貴社のソリューションを最初に検討し始めた時の担当者が私でして、現在は小原と浦井が現場での運用を引き継いでいます。当行では、PickUpを導入する前から離脱率の改善を常に重要なテーマとして位置づけていました。さまざまな手法を試してきた中で、最も高い可能性を感じたのが貴社のサービスでした。
浦井様: 私は主に資産運用領域の非対面施策を担当しています。具体的にはNISAや投資信託など、比較的長期的なナーチャリングが必要なものが中心です。
資産運用領域の非対面チャネルの強化に本格的に取り組み始めたのは約2年前です。それまでは資産運用=顧客と直接お会いしての提案が主流だったのですが、顧客ニーズの変化などを踏まえ、今ではLINEなどを活用して、時間をかけて顧客と信頼関係を育んでいく形が少しずつ整ってきたところです。
小原様:私はカードローン、自動車ローン、教育ローンといったローン領域の商材において、非対面でのデジタル推進を担当しています。主に広告まわりやLINEを活用したデジタル施策の実行を担っています。
私は中途入社で、前職では広告代理店に在籍し、金融機関を中心としたデジタルマーケティングの支援に携わっていました。マーケティング施策の精度を高めながら、顧客にとってストレスのない申込導線をつくることを日々意識しています。
「もったいない」が出発点
──PickUp導入前、どのような課題を感じていらっしゃいましたか?
市川様:大きく2つの課題がありました。1つ目は、新しい顧客を獲得するために、GoogleやYahoo!などのプラットフォームを使ったネット広告を継続的に展開していましたが、広告を展開して商品・サービスページに来訪いただいても、実際に申し込みまで至るユーザーはごく一部でした。かけたコストに対して費用対効果が見合っているのかや、いかに離脱を防ぐかという悩みが常にありました。
──離脱が多かったのでしょうか?
市川様:はい、多かったです。Web広告やSEO施策でサイトに訪問いただいても、最終的に申込まで進まれるのはほんの一部で、8〜9割のユーザーは途中で離脱してしまうのが現実でした。これは業界全体の傾向でもありますが、やはりその数字を見るたびにもったいなさを感じていました。
ネット広告領域では、これまでもcookieを活用したリターゲティングや、各種離脱防止施策を実施してきました。たとえば、Web接客ツールを使ってポップアップを出したり、入力フォームの最適化を図ったりと、基本的な対策は一通り行っていました。ただ、それでも一定数は離脱してしまいます。
そのため、離脱後も追いかける施策として、メール配信やリターゲティング広告を使ったアプローチを行ってきましたが、最近ではcookieレスの影響もあり、なかなか思うように追いきれないという課題が出てきました。
──なるほど。2つ目の課題は何だったのでしょうか?
市川様:もう1つは、常陽銀行の口座をお持ちのお客さまへのアプローチですね。現在、個人の稼働口座数として約200万先を超えるお客さまにお取引をいただいています。これだけの顧客基盤があるのに、そこに対してデジタルチャネルを通じたアプローチがまだまだできていない、という感覚がありました。
どうしても外部への広告や集客施策に目が向きがちですが、本来であれば既にお取引のある顧客に、もっと丁寧に、適切なタイミングでサービスを届けるべきだと考えています。
外部ではなく、内部の各PRチャネルを活用することで、広告コストも削減も期待でき、結果的に満足度の高い提案にもつながります。外部からの流入の強化と顧客データの利活用、その両輪をいかにバランスよく設計していくかが、私たちにとって大きなテーマでした。
数字と体制の両方で見えた「導入する意味」
──PickUpの導入プロセスについても教えてください。
市川様:もともと、リターゲティング広告を通じて離脱後のユーザーに再度アプローチをしていくという施策には一定の成果がありました。ただ、リターゲティング広告等の広告経由ではなく再来訪されるユーザーもいらっしゃいます。そこで、「離脱して再来訪されないユーザー」に対して、もう一度お申込みにつなげるには、どのような手段が最も効果的かという視点で検討を始めました。その際に、コストに見合った効果が本当に出せるのかという点は非常に重視していました。
他社サービスとも比較しながら、費用対効果をしっかりと見極めた上で、まずはテストマーケティング的にPickUpを初期トライアルとして導入することにしました。数字面の改善が見えたことはもちろんですが、それ以上に良かったのが支援体制でした。
成果レポートを月次で提出いただき、改善提案をもとにシナリオやクリエイティブを調整していく。単に「出して終わり」ではなく、運用にしっかりと伴走してもらえる体制が整っていたことは大きな安心材料でした。
最初はカードローンとフリーローンの2商材で始めましたが、そこから自動車ローンや教育ローン、そしてNISAなどの資産運用領域にも導入を検討していく流れになりました。ここ数年、我々が特に注力している分野だったということもあり、非常にタイミングが良かったです。
やはり銀行の商品は、ユーザーにとって馴染みがあるものばかりではありません。少しでも難しそう、分かりづらいと感じた瞬間に離脱されてしまう。だからこそ、自前のチャネルでしっかりと情報を届ける仕組みが必要だと感じていました。
カードローンの成果が、次の一手を後押し
──そこから自動車ローンやNISAへと展開していかれた理由について教えてください。
小原様:まず前提として、カードローンでの成果が非常に良かったです。導入後、月平均で100〜150件の獲得増という安定的な数字が出ていました。時期によって若干のブレはありますが、手応えのある結果でした。
この安定感があったからこそ、「次もやってみよう」と思えました。教育ローンはシーズナリティによる影響が大きいので、まずは自動車ローンを選びました。
車の購入は、検討し始めて実際の契約まで少し時間がかかります。そこで重要になるのがナーチャリングです。PickUpはMA(マーケティングオートメーション)的な要素があるので、一定のリードタイムがある中でも、定期的にコミュニケーションを取りながら、車の購入を決定し、購入資金を意識し始めたタイミングで「ディーラーローンに流れる前に、私たちのローンを想起してもらう」という形でアプローチできる点に、大きな魅力を感じました。
“いまやらなくてもいい”から、気づいたら始めている状態へ
──NISAへの展開についてはいかがでしょうか?
浦井様:NISAなどの資産運用は、ユーザーにとって“今すぐ必要なものではない”商材です。ローンと違って「何か目的があってお金が必要だから借りる」という明確な動機があるわけではないからこそ、じっくりと時間をかけて関係性を築くナーチャリングの重要性が増すと考えています。
PickUpによる自動車ローンの良好な成果が出てきた頃、ちょうど新NISAの制度が始まり、資産運用領域でも本格的にユーザーとの非対面でのコミュニケーションを充実させようとしていたタイミングでした。これまでは資産運用といえば“窓口でのご案内”が主流でしたが、同じようなご案内をデジタルでも実現できるのではないかと考え、PickUpの導入を決めました。
今後の発展として、ユーザーと「LINEを通じて気軽に相談できて安心」という関係を築くことができれば、自然とNISAを始めるきっかけにもなると期待しています。
商材ごとの設計思想が成果を左右する
──商品によって運用方法も変えているのですね?
市川様:はい、まさにそこは意識して設計しています。たとえばローン系の商品は、ニーズがはっきりしています。「今すぐお金が必要」とか、「車を買いたいからローンを組みたい」といった、いわゆる顕在ニーズが前提にあるので、とにかくスピード感が大事になります。ユーザーの熱が高いうちにアプローチすることを重視しています。
一方で、NISAのような資産運用領域の商材になると、話は変わってきます。こちらは「やってみたい気はするけれど、今すぐじゃなくてもいいかな」という、潜在ニーズをどう育てていくかがカギになります。
そうした異なる背景を持つ商材に対して、PickUpは、設計の柔軟性が高いので、非常に相性が良いと感じています。
成功の裏にあるのは「柔軟な設計」と「地道な改善」
──実際に運用してみて、PickUpのどんな点に魅力を感じていますか?
小原様: 私が運用を担当してから、主に2つの観点で取り組んできました。1つ目は、定常的なナーチャリング施策に加えてのスポット施策の併用です。PickUpの基本設計として、LINE追加後にナーチャリング配信を行う仕組みがありますが、それに加えて、スポットでの施策も積極的に取り入れてきました。
たとえば、季節キャンペーンや短期集中のプロモーションに合わせて、Capexさんと都度やり取りをしながら、スポット配信用のシナリオを組み立てていました。すると、通常よりも1日あたり3〜5件、時には10件近く申し込みが増える日もありました。
こうした単月の“勝負どころ”に合わせた施策が、確実に成果につながっている実感がありましたし、定常配信+スポット施策で配信枠ギリギリまで有効活用することで、コンバージョンの底上げが図れたのは大きな手応えでした。
──スポット施策は、成果が見えやすい分やりがいもありそうですね。2つ目のポイントは何でしょうか?
小原様:2つ目は、ポップアップ表示基準の再設計についてです。これはやや細かい話かもしれませんが、ユーザー体験に直結する部分なので非常に大事なことだと思っています。
たとえば、カードローンのページでは、別のチャットボットツールやWeb接客ツールのポップアップを併用しています。その中でPickUpのポップアップがユーザーに“押しつけがましく”ならないように、Capexさんと綿密に調整を重ねました。
ポップアップの表示タイミングや頻度、秒数などを細かく設定し、「ユーザーに不快感を与えず、適切に反応を促す」絶妙な条件を探しました。結果として、他の施策やメルマガなどとの干渉も最小限に抑えられ、数字としてもきちんと成果が出せました。
──運用現場でのきめ細やかなチューニングが、成果につながっているわけですね。
小原様:はい、まさにそうです。単に仕組みを入れて終わりではなく、実際のサイト構成や他施策との兼ね合いまで含めてカスタマイズしていくことで、より良い成果が出せるんだと改めて実感しました。
──浦井様は、どのような点に可能性を感じていますか?
浦井様:小原が話していた内容は、NISAにも通じる部分が多いと思います。そのうえで、私が特に感じているのは、LINEというチャネルの“生活の中への溶け込みやすさ”ですね。LINEは、皆さんが毎日当たり前に使っているツールです。そういう日常的な場所で顧客と自然にコミュニケーションを取れるのは、非常に魅力的だなと感じています。
たとえばNISAの場合、メルマガで「ドルコスト平均法」などを説明することがあります。もちろんメールだと比較的情報量の多い内容を一度に送れるメリットはありますが、LINEだとカルーセルや分割メッセージを組み合わせられるので、より視覚的に、やわらかく伝えられると感じていて、複雑な内容を説明することにも案外向いている気がします。
もちろん、それは私の感覚だけでなく、今後は実際のユーザーの反応や数値的なフィードバックを見ながら、どう活用していくのがベストかを検討していきたいと思っています。
──確かに、NISAのような「いま始めなくても困らないけど、将来的に大事」なものほど、わかりやすさが鍵になりそうですね。
浦井様:おっしゃる通りです。LINEはメールよりもカジュアルで、開封率も高いですし、生活の中に自然に入り込んでいる。だからこそ、ちょっと気になった時に開いて、「なんとなくわかったかも」という感覚を与えられるような作りにしていきたいです。
今後は、そういったコンテンツ面の工夫も、ぜひ貴社と一緒に取り組んでいけたらと思っています。

次なる展開は「深堀り」と「パーソナライズ」
──今後の展開についても、ぜひ教えてください。
市川様:まず、ここ2年ほどでようやく年間のシーズナリーパターンが1から2サイクル整ってきたところです。通常の訴求と、季節ごとの施策、それぞれである程度の型が見えてきました。これからはその運用にしっかりPDCAを回していくフェーズかなと思います。さらに改善して、より高いコンバージョンにつなげていけたらと思っています。
また、今は資産運用の領域に取り組み始めてからまだ日が浅いということもあり、これまでNISAを中心に施策を展開してきましたが、今後はそこに加えて、既存の常陽銀行のお取引顧客に対して「次の一手」を届けるような動きも意識していきたいですね。たとえば、住宅ローンのような商材は、面白い切り口になるのではと思っています。
小原様:前提として、私自身の位置づけとしては、PickUpを「数あるコミュニケーションチャネルの1つ」として見ています。つまり、ナーチャリングのための手段のひとつですね。今、まさに裏側で進めているのは、NISAやカードローンの配信をそれぞれPickUp単体の施策ではなく、カスタマージャーニー全体の中の1つのチャネルとして組み込んでいくことを目指しています。その中で、貴社(Capex)の提供するコミュニケーションチャネルとしての位置づけも、より精度の高いものに進化させたいと考えています。
具体的には、よりパーソナライズされた設計にしていくこと。もちろん「どこでセグメントを切るか」といった定義づけは必要ですが、そのあたりをさらに深掘りして設計していくことで、顧客一人ひとりにとって“ちょうどいい”接点が作れると思います。
最後に:PickUpを検討する企業へメッセージ
──PickUpのようなソリューションは、どのような業界・商材と相性が良いとお感じですか?
市川様:やはり、購買頻度は低いけれど検討の重要度が高い商材には特に向いていると思います。たとえば住宅ローンや保険、不動産などですね。一度きり、あるいは数年に一度の意思決定であるがゆえに、ユーザーもじっくり情報収集をしたい。でも、その間に接点が切れてしまうともったいない。そのような時に、PickUpのような“自然体のコミュニケーション設計”がとても効果的だと感じています。
浦井様:NISAのような資産運用系もまさにそうですが、ユーザーの中にある「今すぐじゃないけど、いつかやるかもしれない」という温度感って、案外多いですよね。そういう“検討中だけどまだ踏み出せない層”に寄り添うという点で、このアプローチはかなり汎用性があると感じます。即決ではなく、じっくり時間をかけて意思決定される商品であれば、どの業界でも十分に機能するのではないでしょうか。
小原様:私が特に相性がいいと感じているのは、検討タイミングが読みづらい商材ですね。
たとえば自動車ローンやカードローンのような商品って、必要になる時期が人によって本当にバラバラです。今すぐ必要な人もいれば、数ヶ月後、あるいは突然の出費で…というケースもある。
そういった商材に対しては、LINEのような日常生活に近いチャネルが非常に有効です。定期的にそっと情報を届けることで、「あ、そういえば…」と思い出してもらえる。“忘れられない存在”として、常に頭の片隅に残るようなコミュニケーションができる。プッシュ型でありながら、ユーザーにストレスを与えにくいという意味でも、ストック型であるLINEが接点づくりに最適だと感じています。
──カードローンのような一見シンプルな商材にも、工夫の余地があると?
小原様:たとえばカードローンは「お金を借りる」という点ではシンプルに見えますが、その背景にあるニーズは非常に多様です。旅行費用が足りない人もいれば、生活資金が一時的に必要な人、あるいは急な出費で対応が求められる人もいる。利用のタイミングや理由は千差万別ですね。
そうした細かいニーズに合わせて、パーソナライズされたアプローチができるという点でも、LINEのような“One to Oneのコミュニケーションが可能なSNS”は相性が良いと感じています。表面的には一つの商材でも、その奥にある多様な理由や動機に対応できる設計が、今後ますます重要になると思います。
──最後に、PickUpを一言で表すと?
市川様:「離脱防止」ですね。まさに、興味関心がありHPに来訪するも離脱して成約に結び付けられなかったユーザーにしっかりアプローチできる仕組みです。
小原様:私は「逃がさない」ですね。せっかく来てくれたユーザーを、無駄にしないための武器だと思っています。
浦井様:私は「追跡中」です(笑)。ユーザーとの距離感を保ちながら、忘れられない存在であり続ける。それをLINEというチャネルで実現できていると感じます。
──市川様、浦井様、小原様、本日は貴重なお話をありがとうございました。
Capexでは、今後もお客様の事例をご紹介してまいります。その他のインタビュー記事もぜひご覧ください。

インタビュイープロフィール
株式会社ニチイ学館 人財開発事業本部 広告部 広告課 サービスマネージャー
水上 裕介様
株式会社ニチイ学館 人財開発事業本部 広告部 広告課
井上 万夕様
課題
- クッキー利用制限により、再アプローチが難しくなると予想されていた
- 長期検討ユーザーへの継続的な接点が不足していた
- 個人情報入力を伴う資料請求は心理的ハードルが高い状況があった
導入の決め手
- LINEでの接点なら、クッキーに頼らず継続的なアプローチが可能と判断
- PickUpのポップアップによる友達登録がユーザーにとって心理的ハードルが低いと感じた
- ユーザーの興味・関心に合わせたシナリオ設計で中長期的な育成が可能になると考えた
導入後の効果
- クッキーに依存しないLINEマーケティングで、ユーザーとの継続的な接点を獲得
- 長期的検討ユーザーへのアプローチが継続できるようになった
- 資料請求より手軽なLINE登録で、心理的ハードルが下がり多くの友だち登録者を獲得
受講生募集を目的とした広告施策を長年展開してきた株式会社ニチイ学館。しかし、クッキーレス時代を迎える中で、従来型のリスティング広告やバナー広告によるリターゲティング手法は限界を迎えつつありました。
そうした課題を解決するために導入されたのが株式会社Capexが提供するLINEを活用したシナリオベース対話AIサービス「PickUp」です。PickUpを使用することで、お客様との継続的な接点を得ることができた同社が、どのようなシナリオやストーリー設計にして情報を届けているのでしょうか。株式会社ニチイ学館 人財開発事業本部 広告部 広告課のサービスマネージャー 水上 裕介様と広告課の井上 万夕様にお話を伺いました。
課題とLINEマーケティング導入背景

──御社の事業内容について教えてください。
水上様:株式会社ニチイ学館は、医療関連事業や介護事業、保育事業を中心に展開しており、具体的には医療機関の医療事務業務の委託や介護事業所の運営、保育所の運営をしています。また、「医療事務講座」や「介護職員初任者研修」などの教育講座も展開しており、私たちはこれらの受講生募集広告を担当しています。
弊社の広告部のミッションとしては、受講生募集の最大化が大きな目標となっています。そして、人財開発事業本部全体が掲げるミッションとしては、医療事務の受託業務や介護施設の運営を支えるための「人財供給」にあります。受講していただいた方が就業に繋がり、その方が医療や介護の現場で活躍されることこそが、私たちの最終的な目標です。
そのため、例えば受講後に就業してくださる方に対しては、受講料をキャッシュバックする制度なども設けています。このように、受講だけで終わらせるのではなく、その先の就業までを見据えた取り組みを意識しています。
──LINEマーケティングを実施する前に、どのような課題を抱えていましたか?
水上様:LINEマーケティングを実施する前は、リスティング広告やバナー広告を中心に広告運用をしており、自社サイト「まなびネット」への集客を行っていました。しかし、インターネット広告全般の課題として、クッキーの規制が強化されたことがあげられます。この規制によりリターゲティング広告ができず、一度サイトに来訪したユーザーに対して、再度アプローチができなくなる可能性が出てきました。
そのため、クッキーを利用したリターゲティング広告に依存せず、サイトに訪問したユーザーと接点を持つ方法を検討する必要がありました。
──このような課題に対して、LINEを使用したマーケティングを採用された理由は何でしょうか?
水上様:LINEを使用したマーケティングを検討した背景としては、クッキーを使わない形で、一度サイトに来訪したユーザーと接点を持つ方法を模索していたことが挙げられます。クッキーが使えなくなってくることで、一度来たユーザーに対して再度案内することが今後難しくなるという大きな課題があったためです。
その中で、Capexさんの「PickUp」のように、一度サイトに来訪したユーザーに対してポップアップを出し、LINEの友だち追加へと誘導する仕組みがある点が非常に魅力的でした。クッキーを使わずにユーザーと繋がり続ける手段として、LINEを使用したマーケティングは適していると感じたため導入を検討しました。
導入の決め手導入の結果

──LINEを導入する際、決め手となったポイントは何でしょうか?
水上様:LINEを活用した対話システムによる新しいコミュニケーションが魅力的でした。先ほどもお伝えしたように、当時はクッキーの規制が進む中で、従来のリスティング広告やバナー広告だけでは対応しきれなくなるのはそう遠くない未来だと感じていました。
具体的な課題が完全に顕在化していたわけではありませんが、将来的に大きな問題になることを予測していたため、先行してLINE施策を始めておくことで、クッキーレスによりリターゲティング広告が使えなくなっても慌てることがなくなると判断しました。
──LINEマーケティングを導入したことで、どのような成果が得られましたか?
水上様:LINEマーケティングを実施したことで、リスティング広告では届かなかった中長期的なユーザーとの接点が確保できるようになりました。特に、LINEを活用することで、検討期間が長いユーザーに対して継続的にアプローチを続けられる点が大きな成果だと感じています。
例えば、LINE友だち登録をしていただいたユーザーの中には、3ヶ月から6ヶ月後に受講申し込みに繋がるユーザーもいらっしゃいます。リスティング広告では、短期的な成果を狙う形が主流ですが、LINEを活用することで、ユーザーとの関係性をじっくりと築き、将来的な受講につながる確かな成果を感じています。
──PickUpを使用した具体的な施策をお教えください。LINE上でのコミュニケーションやシナリオ設計では、どのような工夫を行いましたか?
井上様:PickUp導入後、まず実施したのは、LINE友だち登録後にユーザーの興味や関心に合わせて分岐する診断形式のシナリオを作成することです。これにより、ユーザーの希望や重視するポイントに応じた情報をピンポイントで提供できるようにしました。
例えば診断で、受講する上で重視するポイントを「費用面」 と回答したユーザーには料金的なメリットをよりアピールできるよう、クリエイティブの順番を変更するなど、興味・関心にあわせて配信内容の工夫をしています。このように、ユーザーごとに最適化したシナリオ設計が効果を上げていると感じています。
──LINEでブロックされないために、どのような工夫をされていますか?
井上様:LINEでの配信では、特に配信頻度を意識しています。例えば、キャンペーンを行っていない時期の配信の場合は月に1回程度に抑え、ユーザーに嫌悪感を与えないよう心がけています。一方で、期間限定のキャンペーン時は講座が安くなるタイミングになるので、ユーザーにとって有益な情報をより多く届けられるよう、週に1回程度の配信を行っています。頻度が負担にならない範囲にとどめてはいるものの、配信頻度を上げることで実際に効果を感じられる場面もあったため、今後も工夫していきたいと考えています。
PickUpについて
──PickUpを導入したことで、意外な効果や気づきはありましたか?
水上様:PickUpを導入して特に感じたのはLINE友だち登録の心理的ハードルの低さです。従来の資料請求と比較して、LINE友だち登録は非常に手軽に行えるため、ユーザーが「まずは試してみよう」と気軽に登録してくれる傾向があります。
資料請求の場合は、住所や連絡先などの個人情報を入力する必要があるため、どうしても心理的な負担が大きくなります。一方でLINE友だち登録は、ボタン一つで完了するため、ユーザー側の負担が大幅に軽減されます。この手軽さが、登録数の増加に繋がっていると感じています。
──Capexのサポート体制について、どのように感じられましたか?
井上様:Capexさんからいただく主要なデータは、LINEの友だち数やポップアップ表示数、そこから友だち登録に至った人数、シナリオの完了率、そして最終的に受講申し込みにどれくらいつながったのかといった内容です。
これらのデータを元に、「この部分のCTR(クリック率)が低いのは、ここがボトルネックになっているため効果に繋がらない」といった具体的な分析をしてくださっています。さらに、その課題に対して「どう改善するか」といった提案もセットで頂けるので、とても親身にサポートしてくださっていると感じています。数字だけで終わらず、改善まで伴走してくれる点がありがたいですね。
水上様:Capexさんは我々の要望に対して、真摯に向き合ってくださっていると常に感じています。今後はより一緒になって施策部分を考えて行ってくださるとありがたいと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。
──PickUpは、どのような課題を抱える企業におすすめだと思われますか?
水上様:やはり教育系の業界には非常にマッチしていると感じます。私たちのような講座提供型のサービスもそうですが、教育分野ではユーザーがコンバージョンに至るまでに時間がかかるケースが多いです。例えば、学習塾や資格取得を目的とする講座などでは、ユーザーがじっくり時間をかけて検討するケースが珍しくありません。そのため、中長期的に接点を持ちながら育成していく必要があります。そうした意味でPickUpのようなLINEを活用して定期的なコミュニケーションが取れる施策はとても効果的に機能すると思います。
また、教育分野に限らず、継続的に商品やサービスを提供している業界にも向いていると感じます。例えば化粧品業界は、リピート購入が前提のビジネスなので、ユーザーごとに合った商品やアドバイスをLINE経由で届けることができれば、継続的な購買促進につなげられる可能性があるかと思います。
井上様:加えて、自社サイトでリスティング広告などを活用して集客している企業にもおすすめしたいですね。「広告を出しても思ったように集客できない」と感じている企業様も多いと思いますが、そういった場合に別の導線からユーザーと接点を作る手段としてPickUpを活用してみる価値があると考えています。既存の広告施策と並行して使うことで、今まで取りこぼしている層にもアプローチできるので、結果的により高い効果が期待できると思います。
水上様、井上様、本日は貴重なお話しをありがとうございました。
Capexでは、今後もお客様の事例をご紹介して参ります。その他のインタビュー記事もぜひご覧ください。
インタビュイープロフィール
株式会社ジェーシービー イシュイング本部 イシュイング推進部 プロパー推進グループ 次長
渡邊 有介 様
株式会社ジェーシービー イシュイング本部 イシュイング推進部 プロパー推進グループ 主務
千葉 真理菜 様
課題
- LPの離脱率が高く、コンバージョンに繋がらなかった
- 受動的な広告経由のユーザーの離脱が特に多かった
- ユーザーのニーズに合った情報提供が難しく、フォローアップができていなかった
決め手
- LINEを活用し、個別のニーズに応じた情報提供ができる点
- Capexのシナリオ設計と、クレジットカード商材への深い理解ができる点
- 双方向コミュニケーションが可能で、お客様との接点を強化できる点
結果
- 離脱率が低下し、コンバージョン率が向上した
- 顧客体験(UX)が向上し、申し込み率が改善した
- ユーザーのニーズにあった内容を定期的に配信し、長期的な申し込み増加に繋がった
クレジットカードのプロパーカードにおけるオンライン新規入会獲得で、広告からLPへの流入は確保できていたものの、離脱率が高く、コンバージョン率の向上が課題となっていた株式会社ジェーシービー。特に、情報量が多いクレジットカードという商材の特性上、ユーザーの多様なニーズに応じた情報提供が難しく、フォローアップ施策が求められていました。
この課題を解決するためにJCBが導入したのが、Capexが提供する「PickUp」です。LINE公式アカウントを活用し、ユーザーの状況やニーズに合わせた情報提供を可能にするこのサービスは、顧客体験(UX)の向上とコンバージョン率の改善に寄与しました。
今回、JCBがPickUpをどのように活用し、どのような成果を上げたのか、また、課題解決に向けた取り組みの背景などについて、イシュイング本部 イシュイング推進部 プロパー推進グループの渡邊 有介様と千葉 真理菜様にお話を伺いました。
LPへの流入は確保できても、離脱率の高さが課題に

──PickUp導入以前、どのような課題を抱えていましたか?
渡邊様:ウェブ広告からLPへの流入は一定数確保できていましたが、多くのユーザーが離脱してしまう点が大きな課題でした。特に、ディスプレイ広告など、ユーザーが自発的に検索や行動を起こしたわけではない広告経由でLPに訪れたユーザーの離脱率は顕著で、費用対効果の面でも改善が急務でした。せっかく広告費をかけてLPに誘導しても、コンバージョンに至らなければ意味がありません。そのためフォローアップ施策の強化が必要な状況でした。
千葉様:私が担当しているプロパーカードのウェブチャネル新規獲得業務においても、LP制作やSEO対策など様々な施策を行っていましたが、LPからの離脱率の高さは常に課題として認識していました。特にゴールドカードのLPでの離脱率が高く、新規顧客獲得のボトルネックとなっていました。
──課題解決のために、どのような取り組みを行っていましたか?
渡邊様:課題解決のために、リターゲティング広告の活用やLPの改善、SEO対策などの多角的な施策に取り組んできました。リターゲティング広告には一定の効果が期待できる一方で、広告コストの増加という新たな課題も浮上していました。また、ユーザーのニーズが絶えず多様化している今の状況を考えると、画一的なアプローチだけでは対応しきれないと強く感じていました。
そのような流れがあり、自社メディアを強化してユーザーとのコミュニケーションをより深めることで、より効果的なコンバージョンの獲得を図りたいと考えるようになりました。具体的には、ユーザー一人ひとりのニーズに合わせた情報を提供し、疑問点にもきめ細かに対応することで、コンバージョン率をさらに高められるのではないかと期待しています。
千葉様:ウェブ広告以外の流入経路の強化としてSEO対策にも力を入れていました。しかし、検索流入でLPに訪れたユーザーも、期待していた情報と異なるとすぐに離脱してしまうケースが多く、SEO対策だけでは限界がありました。そこで、LPに訪れたユーザーをいかに自社のプラットフォームに繋ぎとめ、継続的にコミュニケーションを取れるかが重要だと考えました。
PickUp導入の理由は双方向コミュニケーションの実現
──なぜPickUpを導入しようと思ったのですか?
渡邊様:PickUpはLINE公式アカウントと連携することで、情報提供だけでなく、会員様からの質問や疑問にも対応できますし、申し込みの背中を押すコミュニケーションが取れるサービスになると考えました。また、LINEは多くのユーザーが日常的に利用しているツールなので、ユーザーとの接点を維持しやすく、継続的なコミュニケーションを図る上で最適なプラットフォームだと考えました。
──他のツールとの比較検討は行いましたか?
千葉様:はい、ユーザーの離脱を防ぐためのツールをいくつか検討しました。動画を使用してユーザーの悩みにマッチした解決策を提示するサービスなども検討しました。しかし、最終的にPickUpを選んだ決め手は、LINE公式アカウントとの連携、ユーザーに合わせたシナリオ設計によるパーソナライズ化されたコミュニケーション、そしてCapexさんの手厚いサポート体制でした。特に、Capexさんの担当の方からは、クレジットカードという商材の特性を理解した上で具体的な提案をいただき、信頼感を持つことができました。
──LINE公式アカウントは元々運用されていたのでしょうか?
渡邊様:PickUpの導入に合わせてLINE公式アカウントを開設しました。情報量の多いクレジットカードという商材では、ウェブサイト上での一方的な情報提供だけではユーザーの理解を深めるのが難しいと感じていました。LINEであれば、チャット形式でインタラクティブなコミュニケーションが可能となり、ユーザーの疑問や不安に寄り添いながら、よりパーソナライズ化された情報提供ができるのではないかと考えました。また、LINEは多くのユーザーにとって身近なツールであるため、ユーザーとの接点を維持しやすく、関係性を構築していく上で有効な手段だと判断しました。
カード選びの迷いを解消し、納得感のある申し込み体験を提供
──JCB様の全カード券面で導入されたのでしょうか?
渡邊様:最初にPickUpを導入したのは、ゴールドカードです。これは他のカードと比べてゴールドカードの離脱率が高かったからです。課題感が一番大きかったゴールドカードで導入をし、数字が改善するかを確認したいと思いました。
──PickUp導入後、どのような成果がありましたか?
渡邊様:PickUp導入後、ゴールドカードのLPにおける離脱率が低下し、コンバージョン率が向上しました。具体的な成果数値は述べられていませんが、一定の改善が見られました。これは当初の想定を上回る成果で、非常に嬉しく思いました。この成功を受けて、現在ではゴールドカード以外の複数のカードでも横展開して、PickUpを導入して運用するようになりました。
──顧客体験はどのように変化しましたか?
千葉様:ユーザーに合わせたシナリオ設計によって、ユーザー一人ひとりのニーズに寄り添ったコミュニケーションが可能になりました。例えば、カード選びに迷っているユーザーに対して、適切な情報をシナリオ形式で提供することで、納得感を得られる仕組みを構築しました。また、ユーザーが抱える疑問や不安に迅速に対応できるようになったことも、顧客体験の向上に繋がっていると感じています。
──具体的な顧客体験向上のエピソードはありますか?
千葉様:Capexさんからの提案でシナリオをシンプルにしたことで、コンバージョン率が向上したことがあります。PickUp導入時点では、「診断ルート」と「情報提供ルート」の2つのルートを用意していました。「診断ルート」はカードのことをいちから教えて欲しいタイプの方が行くルートで、「情報提供ルート」がある程度の知識がある方が進むルートです。しかし、「情報提供ルート」はコンバージョンに寄与しなかったため、削除することになりました。
──ルートをひとつにしたことでどのような結果になりましたか?
千葉様:シナリオを「診断ルート」に絞ったことで、コンバージョンがかなり上がりました。シナリオだけではなく、ユーザーの導線や行動パターンを意識したUI設計にすることの重要さを再認識した結果になったと感じています。
──コンバージョンまで時間のかかるユーザーへの対策をお教えください。
千葉様:一度登録いただいたLINE友だちには、友だち登録をした1週間後のリマインド配信や、ユーザーをナーチャリングしながら新規入会キャンペーンの案内を行って後押しをするなど継続的なアプローチをしています。これにより、登録後すぐにコンバージョンに至らなかったユーザーにも、改めて申し込みを検討いただく機会を提供できています。他にも友だち登録後一定期間が経過したユーザーに、改めてカードの魅力やメリットを伝えるシナリオを配信する施策も行っています。これらの施策を通じて、ロングテールのコンバージョン促進にも力を入れています。
──複数枚のカードで運用して分かったPickUpの活用方法などはありますか?
渡邊様:マス広告のように広い方々へ届く広告を出稿した際に、PickUpは本領を発揮するのではないかと考えています。弊社のプラチナカードは、マス広告を出稿するタイミングでPickUpを開始しました。マス広告を出すとたくさんの方々がLPに流入してくれますが、多くの方がカードに対しての理解が浅い状態で来られます。そのような方々に対して、カードの理解を促したり、ナーチャリングをすることができるため大きな効果が期待できるのではないかと感じています。
PickUpの導入で離脱率を抑えコンバージョンを高める
──Capexのサポート体制はいかがでしたか?
千葉様:Capexさんのサポートは非常に手厚く、とても助かっています。月に1回行われる定例ミーティングに加えて、日々のメールや電話でのやり取りを通して、密にコミュニケーションを取らせてもらっています。また、Capexさんからの提案は、細かい指標を元にされているので説得力があり、現状の改善点が特定しやすくなるためとても心強いです。さらに、キャンペーンの切り替えなどの作業も短いスパンでご依頼させていただくこともありますが、その度に柔軟に対応いただいている印象があります。
最後に、我々の商材は結果を出すのがとても難しいと考えています。それでも一生懸命に取り組み、結果にコミットしようと行動してくださる姿勢が、日々のやり取りからとても伝わってきます。
──PickUpはどのような企業におすすめでしょうか?
渡邊様:マス広告などで幅広い層にアプローチしたけど、すぐに離脱をされてしまってコンバージョンに繋がらないという課題を持つ企業におすすめです。PickUpを導入することで、LINEを通じてユーザー設定を深化させて、パーソナライズ化されたコミュニケーションで顧客体験を提供することで、コンバージョン数を向上させることが可能になります。
千葉様:顧客接点の強化に課題を持つBtoC企業様すべてにおすすめです。PickUpを活用することで、新規顧客獲得だけでなく、既存顧客との関係構築にも役立ちます。特に、情報量が多く、顧客にとって理解が難しい商材を扱っている企業様には、PickUpの丁寧なコミュニケーションが効果的だと思います。お客様一人ひとりのニーズは様々あって、その方たちに最適なシナリオを発信できるため、顧客接点に課題を持たれている企業であれば効果がより発揮するのではないでしょうか。
渡邊様、千葉様、本日は貴重なお話をありがとうございました。
Capexでは、今後もお客様の事例をご紹介してまいります。その他のインタビュー記事もぜひご覧ください。

インタビュイープロフィール
日本生命保険相互会社 営業企画部担当部長
大内田 鹿郎様
課題
- 生命保険は形がない商材のため、若年層に必要性を理解してもらいにくかった
- 以前は保険会社の営業職員やお客様の身近な方々からの対面での勧めがあったが、そうした機会が減少し保険理解が進みにくくなっている
- SNSやデジタル広告などを行っていたが、一方通行の情報発信になりがちで双方向のコミュニケーションが難しかった
導入の決め手
- Capexから、生命保険の特殊性(将来の不安を汲み取る提案など)をよく理解した提案をいただけたこと
- AIの誤回答(ハルシネーション)対策や、セキュリティ面への信頼感があった。また、「できること・できないこと」を明確に伝えてくれるため、社内への期待値の調整がしやすかった
- お客様との双方向の会話を通じて、雑談を通じて少しずつ保険の必要性を伝えられるキャラクタープラットフォームに魅力を感じた
結果
- キャラクターとの会話をきっかけに、アポイント取得率が向上した
- 「保険についてもっと知りたい」という声が多く寄せられ、キャラクターとの会話が心理的ハードルを下げる手段となった
- 若年層だけでなく、40〜50代の利用も多く、長く使ってもらえる傾向があった
若年層へのアプローチに苦戦していた日本生命保険相互会社。若年層に認知してもらうために様々なデジタル施策を試みていた同社ですが、従来のデジタル施策では一方通行の情報発信が中心で、お客様と双方向のコミュニケーションができていないことに課題を感じていました。そのような課題を解決する手段として導入したのが、デジタル上で双方向の対話コミュニケーションを可能にするキャラクタープラットフォームです。
今回、日本生命保険相互会社がキャラクタープラットフォームをどのように活用し、顧客との継続的なつながりを生み出したのか、導入の背景や具体的な施策・そして得られた成果について、日本生命保険相互会社営業企画部の担当部長 大内田 鹿郎様にお話を伺いました。
 若年層の保険加入を阻む「ニーズ潜在型商品」という特性
若年層の保険加入を阻む「ニーズ潜在型商品」という特性

── キャラクタープラットフォームを導入する以前の課題をお教えください。
大内田様: 生命保険は、他の消費財と異なって顧客が自発的に購入するのではなく、将来いつ起きるか分からない不安に対して購入するため、若年層に対して必要性を理解していただくのが、なかなか難しいという課題がありました。
以前は、営業職員が職域(企業や団体などの従業員が働く現場)で直接若年層と接触して保険の必要性を説明したり、または若年層の方々と同じ職場の先輩社員が対して「保険に入っておいた方がいいよ」と勧める文化がありました。しかし、近年はそうした機会が減少し、保険への理解が進みにくくなっています。
── そのような課題に対して、これまでどのような施策を行ってきましたか?
大内田様: これまで営業企画部では、SNSやデジタル広告を活用して保険の情報を発信してきました。また、結婚式場などの異業種の企業と連携し、ライフイベントをきっかけに保険の必要性を伝える試みも行っています。
しかし、どの施策も基本的には一方通行の情報発信になってしまい、お客様と双方向のコミュニケーションができない点が課題でした。お客様が持つ潜在的な不安や疑問に寄り添い、保険の必要性をより深く理解してもらうことが難しかったのです。その結果、販売件数の拡大にはつながりにくい状況が続いていました。
生命保険の必要性を双方コミュニケーションで理解してもらう
── 双方向のコミュニケーションに課題を抱えていらっしゃる中で、キャラクタープラットフォームの説明を初めて聞いたときの印象をお教えください。
大内田様: 最初にキャラクタープラットフォームを拝見して感じたのは、キャラクターの可愛らしさと親しみやすさでした。また、キャラクタープラットフォームでは、双方向で会話を進めながら少しずつ情報を共有できる体験が得られるのが新鮮でした。この点は、我々が課題と感じていたデジタル上の一方通行の情報収集とは異なる体験を提供できると考えました。
生命保険は自発的に購入されることが少なく、需要を喚起する仕組みが求められます。キャラクタープラットフォームなら、お客様に対して、会話を通じて少しずつ生命保険の必要性を理解していただけるのではないかと考えました。
── キャラクタープラットフォームを導入するにあたって、一番大きな決め手は何でしたか?
大内田様: 一つ目は、Capexさんが生命保険営業の特殊性を非常によく理解してくださっていたことです。保険は日用品のような消費財と比べると、売り方や提案方法が異なります。特に、お客様の将来の不安を汲み取りながら提案する必要があるのですが、Capexさんはその点を的確に捉えた提案をしてくれました。
また、「できること・できないこと」を明確に伝える姿勢にも信頼感を抱きました。セキュリティ面でも、AIの誤回答(ハルシネーション)対策として、例えば、NGワードの制御や個人情報のチェック機能・体制が整っており、安心して導入を進めることができました。
いかに自然な流れで「保険の必要性」に気づいてもらうか
── 「みらい」というキャラクター名の由来や、キャラクター設計などで工夫された点をお教えください。
大内田様: 「みらい」という名前は、当社の商品「みらいのカタチ」に由来しています。また、生命保険のデジタルマーケティングが今後さらに発展するように、「未来に花開いてほしい」という願いも込めています。
キャラクターのデザインは、入社3年目の女性社員が中心に行い、若年層だけではなく幅広い年代に受け入れられるように設計をしました。ただ、ペルソナを厳密に設計することはしていません。お客様にみらいちゃんとの会話体験を楽しんでもらいながら、生命保険の必要性を感じてもらうシナリオの設計はCapexさんに相談しながら決めさせていただきました。
── 生命保険の必要性を感じてもらうために、どのようなシナリオ設計にされたのでしょうか?
大内田様: 生命保険の営業では、いかに自然な流れで「保険の必要性」に気づいてもらうかが重要です。そのため、みらいちゃんとの会話の流れの中でも無理なく保険の話題に入れるよう工夫しました。
例えば、お客様と趣味の話をしている際に、「スポーツが好き」という回答をいただいたら、「スポーツをしているとケガのリスクがありますよね」といった形で話を進めます。このように押しつけがましくなく、会話の延長で自然に保険の必要性を感じてもらえるシナリオ設計を重視しました。
予想以上に多かった、「保険についてもっと知りたい」という声
── キャラクタープラットフォーム導入後、実際にどのような変化が現れましたか?
大内田様: 今までは一方通行の情報発信でしたが、キャラクタープラットフォームを導入したことで、会話を通じて少しずつ保険の理解を深めてもらえるようになったと感じています。その結果として一番分かりやすい成果はアポイントの取得率です。キャラクターとの会話をきっかけに、アポイントの取得率が一定程度向上しました。
また、意外だったのは40〜50代のお客様の利用が想定以上に多かったことです。キャラクタープラットフォームは主に若年層が利用することを想定して導入しましたが、むしろ中高年層の方が長く使ってくれたという結果が出ています。中高年層の方々にとって、キャラクターとの会話が気軽に情報を得られる手段になっていると感じました。
── 2024年12月10日から2回目のPoC(実証実験)を実施されていますが、1回目を含めてどのような形で実施されているのでしょうか?
大内田様: 1回目のPoCは営業職員を通じて、職域で疎遠になっている既存のお客様にLINEやメールでキャラクタープラットフォームを案内する形で実施しました。お伝えする範囲を限定した理由として、初めての利用なこともあり、お客様からマイナスの反響がないかをチェックするのが目的です。結果としては危惧していたクレームはなく、ポジティブな意見が多い結果になりました。そして、2回目のPoCでは告知をせず、オフィシャルホームページの商品ページにみらいちゃんを設置し、訪問者が利用できる形にしています。
──1回目のPoCと2回目のPoCで、シナリオなど変更した点はございますか?
大内田様:キャラクタープラットフォームに期待しているのは、双方向のコミュニケーションにより、保険の必要性を知ってもらうことなので、第1回目のPoCよりも保険のニーズ喚起を意識してシナリオを変更しました。しかし、突然保険の話しをしてしまうとお客様の体験が悪くなってしまうので、そこに辿り着くまでの設計も重要視して設計をしています。
これらのシナリオ変更は、キャラクタープラットフォームでお客様がどこで離脱されたのかをデータとして見える化できているからです。我々としては保険を売りたいという思いはありますが、お客様との日常会話の重要性が第1回目のPoCで分かったので、そこのバランスを意識して修正を行うことができました。
── データ分析を通じて、新たな気づきはありましたか?
大内田様:キャラクタープラットフォームをご利用いただいたお客様にアンケートをお答えいただいているのですが、「保険についてもっと知りたい」という回答が予想以上に多かったことに驚きました。通常、営業職員が説明すると「売り込まれるのでは?」と警戒される方もいらっしゃいますが、キャラクターとの会話ならそのような心理的ハードルが低くなり、気軽に質問できる環境が整っていると感じています。
自然な会話を通じてお客様との距離を近づけたり、情報提供・需要喚起を行いたいと考えている企業におすすめ


 ── 今後、キャラクタープラットフォームをどのように活用していきたいと考えていらっしゃいますか?
── 今後、キャラクタープラットフォームをどのように活用していきたいと考えていらっしゃいますか?
大内田様: 現状ではホームページに設置している段階ですが、より多くのお客様に利用してもらう方法を模索しています。営業職員も活用して連携を深めるのか、それともWeb上での活用を広げるのかはまだ試行錯誤中です。
将来的には、キャラクターとの対話ログを活用し、リアルな営業活動とも連携させたいと考えています。例えば、資料請求をしたお客様がキャラクターと年金の話をしていたなら、インサイドセールスがその情報を参考にしながら対応できるようにする。そうすれば、より精度の高い提案が可能になると考えています。
── 最後に、キャラクタープラットフォームはどのような企業におすすめでしょうか?
大内田様: 保険業界はもちろんですが、自然な会話を通じてお客様との距離感を近づけたり、情報提供や需要喚起を行いたいと考えている企業に特に向いていると思います。例えば、一方通行の情報発信では効果が出にくいと悩む企業には、顧客との関係性を築く手段として有効です。キャラクターを活用することで、お客様との関係性を築きながら、自然な形で商品やサービスの価値を伝えられる。こうしたアプローチにはまだまだ可能性があると思います。

インタビュイープロフィール 株式会社セブン銀行 部署:バンキング統括部 役職:グループ長 氏名:高田 大輔 様 株式会社セブン銀行 部署:バンキング統括部 役職:調査役 氏名:勝山 浩輔 様
インタビュイープロフィール
株式会社セブン銀行バンキング統括部グループ長
高田 大輔 様
株式会社セブン銀行バンキング統括部調査役
勝山 浩輔 様
課題
- Web広告やLPを通じた集客はできていたものの、コンバージョン率に課題感があった
- 従来のWebマーケティングでは、申し込みにあたっての顧客の心理的な不安を解消しきれなかった
決め手
- 成果報酬型でリスクを抑え、CPAを通常広告の70%に設定できているコストパフォーマンス
- LINEを活用し、クッキーレス環境でも継続的な顧客接点を持てる仕組み
- 柔軟なシナリオ設計と顧客ニーズに合わせた運用が可能な機動性
結果
- 初回シナリオ完了率が70%から80%台後半まで向上し、顧客体験を改善
- 顧客の不安を解消、サービスの利用意向を高め、申し込みまでの体験を改善
- 登録から220日後の申し込みの実現など、長期的な顧客接点維持に成功
カードローン事業におけるマーケティング課題を抱えていたセブン銀行。Web広告やランディングページを通じて多くの見込み顧客を集めることには成功していたものの、そこから申し込みに至るまでのコンバージョン率に課題がありました。この「あと一歩」を後押しするために、同社が導入したのがLINEを活用したPickUpです。
今回、PickUpをどのように活用して課題を解決し、顧客との継続的なつながりを生み出したのか、具体的なエピソードを交えて詳細を伺いました。セブン銀行バンキング統括部のグループ長 高田 大輔様と、同じくバンキング統括部 調査役の勝山 浩輔様にお話を伺いました。
カードローンの「あと一歩」を後押しする新たな仕組みの導入

──PickUp導入前には、どのような課題があったのでしょうか?
高田様:セブン銀行では、カードローンのサービスを提供しています。従来の取り組みはカードローンを必要とする方には興味を持っていただけるのですが、Web広告やLPを通じて集客しても、そこからお申し込みに至るまでのコンバージョン率が課題でした。そこで、この「あと一歩」を後押しする仕組みが必要だと考えていました。
一般的なWebマーケティング施策、例えばLPの最適化やキーワード変更、キャッチコピーの見直しなどは行っていました。しかし、それだけでは補えない部分がありました。
──PickUp導入に至るまでの経緯はいかがでしたか?
高田様:当初はカードローンのような商材に本当に適応できるのか、不安な部分が多かったですね。カードローンは、必要な方には便利な商品ですが、需要が強くないお客様にとっては逆にネガティブに受け取られる可能性もあるんです。そうした商品の特性上、繰り返しアプローチすることが逆効果になるのではないか、という懸念がありました。
また、Web広告やLPからLINEへの導線を作ったとしても、お客様がそこまで移動してくれるのか、お客様を追いかけるような行為がお客様の体験を阻害することにならないのかという疑問もありました。さらに言うと、LINEでのやり取りがどれだけお客様の背中を押せるのか、半信半疑だったのが当時の正直な気持ちです。
ですが、チーム内で議論を重ねていくうちにお客さまの申込体験を損ねず、むしろ向上させることができるのではと感じるようになりました。
勝山様:今はクッキーレス時代で、お客様との接点を継続的に持つこと自体が非常に難しい状態です。そういう背景もあり、LINEという普段使い慣れたツールを活用して、双方向のコミュニケーションを図れるという点に可能性を感じていました。これは新たな集客チャネルとして、またお客さまにとっても弊社のカードローンに対する不安を払しょくし納得してお申し込み頂けるようになるんじゃないかと考えたんです。
──導入までの期間はどれくらいでしたか?
勝山様:比較的早かったですね。話をいただいてから3~4ヶ月程度で導入が決定しました。セブン銀行では新しい取り組みを進める際、通常もう少し時間がかかることも多いのですが、今回はかなりスムーズに進んだんじゃないかと思います。
UI改善などの細やかな施策で初回シナリオ完了率80%台後半を実現
──PickUp導入にあたって、他社サービスとも比較検討されたんでしょうか?
高田様:類似サービスが他にいくつかありましたので比較検討はしました。そして最終的にはPickUpと別のサービスの2つを検討することになりました。
──なぜPickUpを選ばれたのでしょうか?最終的な決め手は…?
高田様:やはりコストパフォーマンスが非常に高かった点が決め手の一つでした。他社とも比較検討したんですけど、成果報酬型でリスクを抑えられる点や、CPAが通常のWeb広告の70%で設定できた点は非常に魅力的でしたね。他社も検討しましたが、PickUpの方が、私たちにとって導入のリスクが少ない点が非常に大きかったと思います。
──PickUpを導入して、具体的にどのような施策を展開されたのでしょうか?
勝山様:PickUp導入当初、初回シナリオの完了率は約70%でした。我々は70%でも想定以上の成果でしたが、Capexさんから80%から90%までは伸ばせるはずだと予測を聞いていました。そして、Capexさんがその原因を探るためにデータを分析したところ、顧客層の年代が高めであることが分かったんです。
そこから、Capexさんが選択肢の文字の小ささが視認性に影響している可能性があると仮説を立ててくれました。初期段階ではLINEデフォルトの小さな文字列で選択肢を表示していたのですが、これをボタン形式に変更して文字サイズも大きくしたところ、完了率が70%から80%台後半まで向上したんです。
──他にも、効果のあった施策がありましたら教えてください。
高田様:LINEリッチメニューも活用しています。例えば、お客様はやはり「自分がローンの審査に通過できるのかどうか」というところを非常に心配されるんです。そこで、本申込の前にリッチメニューを活用し、お客様が何度でも審査診断を行えるようにしたんです。すると、1人当たり平均1.55回診断を行うという結果になり、不安を解消しながら最終的に申し込みをいただけるようになりました。
勝山様:他にも当初30日間で終了するシナリオだったところを、年間で配信するシナリオを追加で作成し、季節ごとの資金需要に応じたメッセージ配信を行ったのも効果的でした。年末年始には「帰省やお年玉での出費をサポートします」といったコンテンツを配信するといったようなシナリオです。これもCapexさんからのご提案だったんですが、私たちにはなかった視点だったので非常に助かりました。結果的に、登録から220日後に申し込みがあったケースもあり、長期的な接点を維持する重要性を実感しました。
PickUpを導入して顧客の不安を和らげ、満足度向上を実現

──PickUpを導入してみて、お客様からはどのような反応がありましたか?
勝山様:カードローンという商材は、お客様からの声がなかなか届きにくい商材です。そのため、当初はPickUpを導入したことによるお客さまからのお問い合わせ等は増えるだろうと予想していたんですが、想定していたような反応はほとんど無く、これは嬉しい誤算でした。
──PickUp導入が、お客様の満足度向上につながったということでしょうか?
高田様:そうだと思います。ローンという商品は、どうしても心理的な障壁を伴うものだと思っています。「本当に必要なのか」「返済できるのか」といった不安を抱えるお客様も多いと思うんです。これまでWeb広告やLPでは捉えきれなかったこうした不安が、LINEというツールを通じた双方向のコミュニケーションによって少しずつ解消されていると感じています。結果的に、ローンという商品を「便利に使ってみよう」と思っていただけるきっかけになっているのではないでしょうか。
PickUpは心理的なハードルが高い商材にこそおすすめ
──今までの取り組みの中で、印象に残っているサポートなどはございますか?
勝山様:Capexさんに助けられていると感じるのは、ユーザーのインサイトを弊社よりも深く理解していただいているところです。私たちの事業内容はもちろん、その先のユーザーのことも理解してくださっているので、良い提案につながっているのだと感じます。
──PickUpを他の企業にもおすすめするとしたら、どのような企業に向いていると思いますか?
高田様:PickUpは、お客様が心理的な障壁を感じやすい商材を扱う企業にとって非常に相性が良いと思います。例えば、金融商品はもちろんですが高額な契約が必要なサービスなどで、顧客が「ちょっと不安だな」と思うポイントを解消できるツールとして最適ではないでしょうか。お客様に寄り添いながら、信頼を築きたいと考えている企業にはおすすめのサービスかと思います。